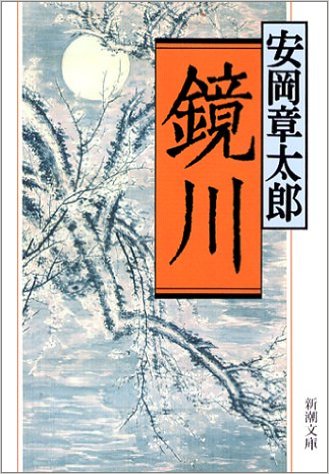人間失格/太宰治
「恥の多い生涯を送って来ました」。そんな身もふたもない告白から男の手記は始まる。男は自分を偽り、ひとを欺き、取り返しようのない過ちを犯し、「失格」の判定を自らにくだす。でも、男が不在になると、彼を懐かしんで、ある女性は語るのだ。「とても素直で、よく気がきいて(中略)神様みたいないい子でした」と。ひとがひととして、ひとと生きる意味を問う、太宰治、捨て身の問題作。 Amazon 内容紹介より
太宰治
1909‐1948。本名・津島修治。青森県北津軽郡金木村(現・青森県五所川原市)の地主の子として生まれる。1930(昭和5)年、東京帝国大学(東京大学)仏文科に入学、井伏鱒二に師事、小説家を志す。1933(昭和8)年、同人誌「海豹」に発表した『魚服記』、『思ひ出』という作品で注目され、戦後は人気作家として多くの作品を精力的に発表した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)BOOK著者紹介情報より
マイアイドル太宰治。
中でも人間失格は10回は読んでると思います。
ですが、寂しいことに最後に読んだのはおそらく10年以上前。
夏期講習の合間、不惑にして読む「人間失格」。
新たな発見に満ちていました。
ご存知の方も多いと思いますが、自殺未遂、薬物中毒など自身の体験を下敷きに書いたのが人間失格。
「負」、「破滅」へ向かうの求心力はすさまじいものがあります。
だから、どうしても葉蔵中心、退廃のヒロイズムにあこがれて、自らを重ね合わせてしまうのが、一般的な読み方。
また、一説には10代で卒業する(しなければならない)といわれる太宰治。
その理由は、極端な自意識過剰と自己愛です。
そこを文学まで高め、私小説を完成させたのが一番の功績かと思いますが、
でも、
機会があれば改めて紹介しますが、日本文学において並ぶもののない技巧派の面、また案外ポジティブな面も太宰治は持ち合わせています。
技巧派の太宰でもっとも有名なのは「斜陽」の冒頭
朝、食堂でスウプを一さじ、すっと吸ってお母さまが、
「あ」
と幽かな叫び声をお挙げになった。
「髪の毛?」
スウプに何か、イヤなものでも入っていたのかしら、と思った。
「いいえ」
お母さまは、何事も無かったように、またひらりと一さじ、スウプをお口に流し込み、すましてお顔を横に向け、お勝手の窓の、満開の山桜に視線を送り、そうしてお顔を横に向けたまま、またひらりと一さじ、スウプを小さなお唇のあいだに滑り込ませた。
これほど完璧な冒頭部分は読んだことがありません。
「あ」の一言で、
喪失感、取り返しのつかない後悔、底知れぬ不安を読者に掻き立てます。
そして、「スウプ」、「ひらり」の単語の使い方が見事。
初めて読んだときは、小説、言葉にはこんな力があったのかと衝撃を受けました。
ポジティブな太宰の代表は「パンドラの匣」のラスト。
私は何にも知りません。しかし、伸びる方向に陽の当たるようです。
太宰版青春小説と読んでもいいくらいさわやかな作風、「人間失格」と同じ人物が書いたとは思えない落差がそこにはあります。
ちょっと暗そうで嫌、という生徒は「パンドラの匣(はこ)」を一冊目に持ってくるのもいいかもしれません。
そして、「人間失格」の冒頭。
私は、その男の写真を三葉、見たことがある。
一葉は、その男の、幼年時代、とでも言うべきであろうか、十歳前後かと推定される頃の写真であって、その子供が大勢の女のひとに取りかこまれ、(それは、その子供の姉たち、妹たち、それから、従姉妹たちかと想像される)庭園の池のほとりに、荒い縞の袴をはいて立ち、首を三十度ほど左に傾け、醜く笑っている写真である。醜く? けれども、鈍い人たち(つまり、美醜などに関心を持たぬ人たち)は、面白くも何とも無いような顔をして、
「可愛い坊ちゃんですね」
といい加減なお世辞を言っても、まんざら空お世辞に聞えないくらいの、謂わば通俗の「可愛らしさ」みたいな影もその子供の笑顔に無いわけではないのだが、しかし、いささかでも、美醜に就いての訓練を経て来たひとなら、ひとめ見てすぐ、
「なんて、いやな子供だ」
と頗る不快そうに呟き、毛虫でも払いのける時のような手つきで、その写真をほうり投げるかも知れない。
「ただ一切は過ぎていきます」の有名なラストより、「人間失格」のエッセンスはこの冒頭部分に集約されているかもしれません。
そして、再読した「人間失格」は、意外なほどユーモアがちりばめられていることに驚きました。
ユーモアの天才と言われる太宰治、
こと人間失格に関してはユーモアを封印、遺書として書いたというのが定説ですが、
お道化のくだり、歩道橋のくだり、女性関係のくだり、堀木のくだり、
極めつけはラストのヘノモチンなどなど、
シリアスな場面になればなるほど、必ずクスリとさせるユーモアがあるのです。
ユーモアとペシミズム(悲観主義)は紙一重。
つまり、作中で言うならシノニム(同義語)。
ユーモアと絶望感の同居、
この独特の感覚が今も若い読者をひきつける理由なのでしょう。
また、太宰=葉蔵は退廃的と言われますが、葉蔵はたぐいまれな純粋さを持ち合わせています。
葉蔵が人間を信じられないのは、人間の純粋さを信じては裏切られるからです。
いや、裏切られてもなお信じてしまう、信じない自らを罰する人生が葉蔵なのです。
そして、
本心を隠して本当のことを言わない、自分を棚に上げて他人を見下す、エライ人の前では平気で仮面をかぶる等々、
「人間として当たり前とされる」営みにうまく加われない。
いろいろ努力してきたが、やはり無理だ。
「人間生活」がやっていけない葉蔵はついに「人間失格」となるわけです。
もっと言えば、
戦後、激動の変化を遂げる、手のひらを返したような態度をとる人間たちが「人間」だとするなら、太宰治は「人間失格」で構わないということです。
太宰治的な自意識を「中二病」というのならそうなのかもしれませんが、私は「中二」の側に立ちたいと思います。
自意識万歳、中高生の皆さんは、ぜひ葉蔵の世界にどっぷり使ってください(先日も中二の生徒が読んでましたね)。
そして、「斜陽」や「ヴィヨンの妻」など抑制のとれた作品にも触れてください。
ですが、もうひとつ、
不惑を過ぎたものとしての「人間失格」について。
葉蔵、太宰への全面的な共感を未だに感じるものがいれば、それこそ欺瞞です。
永遠に葉蔵でありたいと思っていても、いつしか葉蔵ではいられなくなっていきます。
中2病だった子供たちも、人生を続ける以上、程度の差こそあれ、やはりいつか、どこかで大人になっていきます。
つまり、作中の父やヒラメにならずとも、葉蔵側でなく、堀木の側に自分が立っていると自覚すべきなのではないでしょうか。
これまで読んできてあまり気に留めなかった一節が今回の再再読で突き刺さりました。
葉蔵が、堀木に向けた、言葉にできなかった言葉です。
「世間というのは、君じゃないか」
という言葉が、舌の先まで出かかって、堀木を怒らせるのがイヤで、ひっこめました。
(それは世間が、ゆるさない)
(世間じゃない。あなたがゆるさないのでしょう?)
(そんな事をすると、世間からひどいめに逢うぞ)
(世間じゃない。あなたでしょう?)
(いまに世間から葬られる)
(世間じゃない。葬るのはあなたでしょう?)
いつの間にか、葉蔵の側から、堀木の側にいた自分(もともと堀木の側にいたのかもしれません)。
「世間というのは、君じゃないか」
太宰治を死に追いやったのは僕やあなたかもしれません。
太宰治の年齢を超えた今、新たに胸に刻んで行こうと思いました。